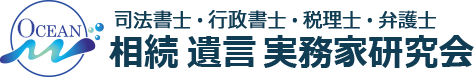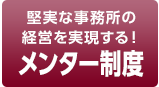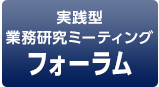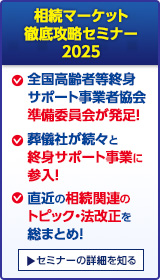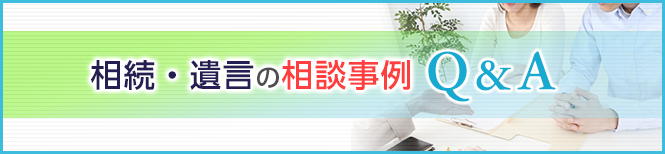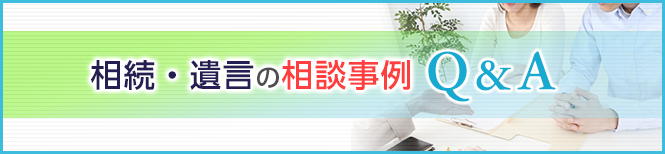
2024年01月17日
Q:遺言の中で遺言執行者として指定されている方の手続きの委任を受ける場合、遺言執行者には第三者を代理人に選任するだけの特別な事情が必要でしょうか?
相談の背景
行政書士の先生からのご質問。行政書士の先生が、遺言の中で遺言執行者として指定されている方から依頼され、遺言執行業務を進めていたところ、銀行から「遺言執行者が復代理人を選任して手続きを進めているのはなぜか」と問い合わせがあった。詳しく話を聞いてみたところ、遺言書の中で復代理人の選任に関する記載がないのだから、「遺言執行者はやむをえない事情がないと復代理人を選任できないはずだ」とのことだった。遺言執行者が手続きを人に任せたいという理由で、第三者に遺言執行業務を委任することはできないのか。
A:遺言執行者の地位を第三者に移転させることの可否は、遺言書が作成された日付によって異なります。
弁護士 森田雅也の解説
従来、民法は遺言執行者の復任権について、遺言書内に特別の記載がない限り、「やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない」と定めていました。
つまり、遺言書のなかで、「遺言執行者は、遺言の執行に際し、第三者にその任を行わせることができる」といった記載がない限りは、復代理人を選任し、遺言執行者の地位そのものを移転させることができませんでした。
しかし、2019年7月1日の法改正に伴い、遺言執行者の復任権については、遺言書内に特別の記載がない限り、「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」と定められることとなりました(民法1016条)。従来は、原則として遺言執行者は復代理人を選任できず、①遺言者が遺言のなかで復代理人の選任を認めている場合、又は②復代理人を選任するやむを得ない事情がある場合のみ、例外的に復代理人を選任することができたのが、法改正によって、遺言者が遺言のなかで復代理人の選任を認めていない場合を除き、原則として遺言執行者は復代理人を選任することができるようになりました。
この「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」とする規定は、2019年7月1日の法改正以降に作成された遺言書にしか適用されません。
したがって、質問者である先生の依頼者が、2019年7月1日よりも前に作成された遺言書によって遺言執行者に指定されている場合、先生は復代理人になることができません。
なお、従来の規定が適用される場合でも、特定の行為のみを第三者に委任することは認められているため、行政書士や司法書士の先生が、預貯金口座の解約や不動産名義の変更について個別に委任を受けることは問題ありません。あくまで「遺言執行者の地位を第三者に移転させること」が禁止されていた点には注意が必要です。
<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
相続遺言実務家研究会では、会員様を対象に無料法律相談窓口を設置しております。
法律問題についてのご質問等ございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://pro.souzokuigon.info/authense/
2024年01月17日
Q:相続人が全国にいる場合の遺産分割協議の進め方を教えてください。
相談の背景
地域の行政書士の先生からのご相談。相続人調査をしていたところ、被相続人には依頼者である子のほかに、前妻との間に複数人の子がいたことが判明。相続人が全国各地におり、依頼者としては全員と話し合いを進める手間よりも、法定相続分で分割して終わらせたいとの意向だが、遺産分割協議をどう進めるべきか知りたい。
A:遺産承継業務を活用し、 手続きを進めましょう。
弁護士 森田雅也の解説
相続人が複数いて全国に散らばっている場合、遺産分割協議を進めるのは容易ではありません。ましてや、今回の事例のように、異母兄弟が判明したような場合では、協議で遺産分割方針を決めるのはより困難を伴います。
このような相続手続きを進める場合、遺産承継業務での受任を検討しましょう。
遺産承継業務は、相続人全員からの委任に基づいて相続人全員の代理人として被相続人の遺産を管理し、遺産分割協議の方針に沿って相続人に分配する業務となります。
この遺産承継業務は、従来弁護士と司法書士にしか認められていない業務でしたが、令和5年3月の総務省の通知により、「行政書士が財産管理を行うことは業務上問題がない」との法令解釈の変更がなされました。
これにより、行政書士の先生でも遺産承継業務を行うことが可能になりました。
なお、遺産承継業務で手続きを進める場合には、「非弁行為」に注意が必要です。
遺産承継は相続人全員の代理人として手続きを進めることができる手続きですが、特定の相続人の代理人としてその方の利益を実現することは、弁護士にしか認められていません。
行政書士の先生が遺産承継業務で手続きを進める場合には、法定相続分での分割が原則となり、例えば依頼者が法定相続分以上の財産を取得出来るように他の相続人に働きかけるような行為は非弁行為に当たります。そのような特定の相続人の利益を実現するために働きかけるような場面では、弁護士にご依頼ください。
<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
相続遺言実務家研究会では、会員様を対象に無料法律相談窓口を設置しております。
法律問題についてのご質問等ございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://pro.souzokuigon.info/authense/
2023年10月04日
Q:地域の司法書士の先生からのご相談。遺産分割協議を進めるために知的障害を持つ依頼者の弟に成年後見人をつけたいが、弟の預貯金を使い込んでいた母親が後見人になると主張している。母親が後見人になることを阻止し、適正な遺産分割協議を実現する方法を伺いたい。
相談の背景
2ヶ月前に依頼者の祖父が亡くなり、父親もすでに亡くなっていたため、叔父と依頼者、依頼者の弟の3人で遺産分割を行うことになった。相続税の納税資金の捻出のために早急に祖父名義の不動産を売却したいが、依頼者の弟に知的障害があるため、遺産分割協議を進めるために成年後見人を選任する必要がある。
弟の成年後見人として 母親が立候補していたが、母親は弟の預貯金を使い込む性格で、依頼者としては母親を弟の後見人にすることには不安を感じている。
母親を成年後見人にすることなく、適正に遺産分割協議を進めたい。
A:専門家を後見人に就任させ、遺産分割協議を進めましょう。
弁護士 森田雅也の解説
成年後見人になれるのは親族だけではありません。近年では、成年後見人には弁護士や司法書士といった専門家が選任されるのが一般的で、場合によっては支援が必要な分野に応じて複数の後見人が選任されることもあります。
今回の相談事例では、母親が後見人として立候補していたため、選任の申し立てと併せて「母親を成年後見人とすることは適切でない」旨の上申書を提出するとよいでしょう。母親が弟の財産を使い込んでいたこと、ゆえに弟が祖父から相続した財産も使い込まれてしまうリスクがあることを丁寧に主張することで、専門家を成年後見人に選任してもらうことができるかもしれません。
今回の相談事例では、遺産分割協議を進めるだけではなく、その後の不動産売却も相続税申告の期限内に行う必要があります。相続の専門家が成年後見人に就任することで、スピーディーに遺産分割を進めることができます。
<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
相続遺言実務家研究会では、会員様を対象に無料法律相談窓口を設置しております。
法律問題についてのご質問等ございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://pro.souzokuigon.info/authense/
2023年10月04日
Q:面識のない相続人との手続きの進め方を教えてください。
相談の背景
都内の行政書士の先生からのご相談。依頼者の父が亡くなり、相続人や相続財産を調査していたところ、父の不動産に祖父の名義が残っていることが判明した。父の相続手続きを進めるにあたり、併せて祖父の相続人調査も追加で進めたが、祖父の相続人にあたる兄弟姉妹5名のうち、既に3名が亡くなっており、代襲相続人も含めると相続人は依頼者も含めて15名に及ぶことが発覚した。
相続人にあたる親族の大半と面識がない状況で、どのように手続きを進めればよいか。
A:相続人にあたる親族全員と連絡をとり、意向を確認しましょう。
弁護士 森田雅也の解説
どれだけ前に発生していた相続であっても、遺産分割の原則が「相続人全員の合意による分割」であることに変わりはありません。そのため、相続人にあたる親族との協議のうえ、祖父の相続手続きを進める必要があります。
今回の事例では、依頼者は自分の兄弟姉妹を除く親族12名とは面識がなく、連絡先も分からない状況ですので、まずは各相続人の住民票記載の住所宛に意向確認のお手紙を送る必要があります。
お手紙で全相続人の意向が確認できれば、そのまま遺産分割協議を進めることができます。
一方、お手紙では意向を確認できなかったり、協力を得られなかったりする場合、家庭裁判所での遺産分割調停で手続きを進めることになります。このとき、家庭裁判所は相続人が複数で所有するような分割方針を示すことを避ける傾向にあります。
こうした場合には、特定の相続人が不動産を取得し、法定相続分相当の金銭を各相続人に分配する代償分割か、不動産を売却し、売却金を分割する換価分割になることが一般的です。
<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
相続遺言実務家研究会では、会員様を対象に無料法律相談窓口を設置しております。
法律問題についてのご質問等ございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://pro.souzokuigon.info/authense/
2023年09月25日
Q:自己破産をした場合の相続財産の受け取り方について教えてほしい。
相談の背景
親族が亡くなり、相続が発生したが、相続人のなかに自己破産をした人がいるため、相続財産を受け取れるのかどうかを不安に感じている。自己破産をした相続人も相続財産を受け取れるのか、受け取れる場合の条件について教えてほしい。
A:自己破産をされた相続人が相続財産を受け取れるかどうかは、自己破産のタイミングによって異なります。
弁護士 森田雅也の解説
自己破産をする場合、自己破産により債権者に分配される財産は、破産手続きの開始時点で破産者が有していた財産に限定されます。つまり、自己破産をされた相続人が相続財産を受け取れるかどうかは、相続財産が破産した方の財産として扱われるかどうかによって決まります。
まず、破産手続きの申立て前に相続が発生していた場合、通常の相続人としての立場になるため、通常通りの遺産分割協議を進めることになります。取得した財産で自己破産を免れることができることが理想ですが、相続財産だけでは債権者への清算が出来ず、自己破産を選択しなければならない場合、相続財産は、破産管財人を通じて債権者へ分配されてしまいます。
次に、破産手続きの申立て後、破産手続き開始決定前に相続が発生していた場合、相続財産は、生活に最低限必要なものと99万円以下の現金を除き、全て破産管財人が管理・処分する権利をもつ「破産財団」に組み込まれます。
つまり、破産手続き開始決定前に相続が発生していた場合、相続することは可能ですが、それらの大半が破産財団に組み込まれ、破産管財人によって、債権者へ分配されてしまいます。
最後に、破産手続き開始決定後に相続が発生していた場合、相続財産は、「破産手続きの開始時点で破産者が有していた財産」としては扱われません。ゆえに、破産開始手続き決定後に得た財産は、破産手続きとは関係のない新たな財産として相続が可能です。
以上より、破産手続き開始決定後の相続発生においてのみ、破産者は相続財産をそのまま受け取ることができます。しかし、相続の発生するタイミングをコントロールすることはできません。自己破産を行う方はタイミングを慎重に検討し、必要に応じて、相続放棄を選択するなど、相続財産が相続人以外の方に受け取られてしまわないような対策が必要です。
<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
相続遺言実務家研究会では、会員様を対象に無料法律相談窓口を設置しております。
法律問題についてのご質問等ございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://pro.souzokuigon.info/authense/